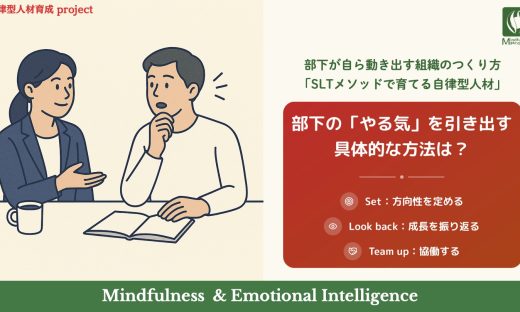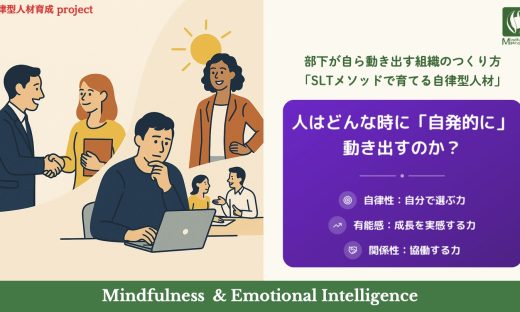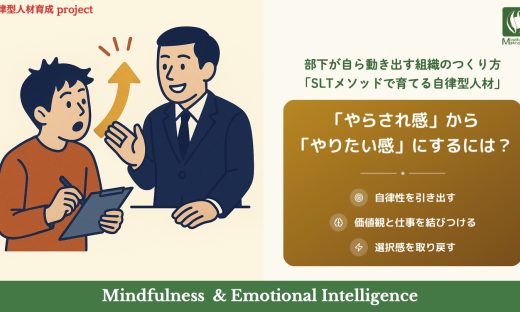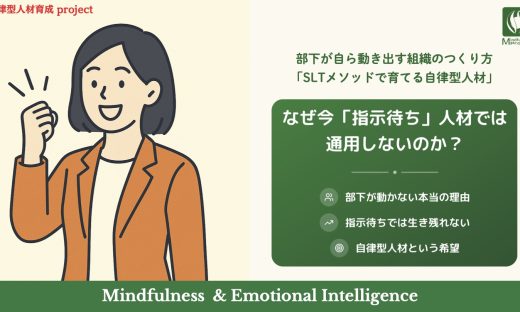第2章:「やらされる人」と「やりたい人」は何が違うのか?|部下の動機を引き出すカギ|「外発から内発」への転換

「頑張ります!」と言っていたのに、なぜ続かないのでしょうか?
定例会議で、「今四半期の売上目標20%アップ」が発表されました。AさんもBさんも、その瞬間「頑張ります!」と元気に答えました。あなたは安心しました。
しかし1週間後、Aさんの動きは鈍くなっていました。「やる気はあるんですけど、なかなか…」と言い訳が増えていきます。
一方、Bさんは週を追うごとに自発的に顧客訪問を増やし、「お客様により良い価値を提供したい」と目を輝かせています。
この「頑張ります」の裏側にある違い、心当たりはありませんか?
実は、この違いの核心にあるのが、動機の質です。同じ「頑張る」という言葉でも、その背後にある動機の種類によって、取り組む姿勢も成果も全く変わってくることが心理学の研究で明らかになっています。
人を動かす2つのアプローチ
ビジネスの現場では、成果を出すために様々な「人を動かす仕組み」が使われています。
外発的動機づけ:報酬と罰則による動機
最も一般的なのが外発的動機づけです。目標達成でボーナス支給、未達だと評価が下がる、ルール違反で叱責される。こうした報酬と罰則による動機づけは、確かに一定の効果があります。
外発的動機づけの特徴
- 報酬・罰則などの外部要因が行動の原動力
- 短期的には効果的で管理しやすい
- 結果が分かりやすく測定可能
しかし、現実の多くの組織では、外発的動機づけの「隠れたコスト」に苦しむ姿が見られます。
外発的動機づけの限界
- 持続性の欠如:刺激がなければ行動が止まってしまう
- 創造性の阻害:「間違えないこと」を最優先に考え、新しい発想や挑戦を避ける
- 関係性の悪化:競争が激化し、協力関係が破綻する
内発的動機づけ:内なる情熱による動機
一方で、全く異なる特徴を持つのが内発的動機づけです。これは外的要因ではなく、「自分の内側から湧き上がる動機」に基づく行動を指します。
内発的動機づけの特徴
- 興味・関心・価値観が行動の原動力
- 学習や成長への自然な欲求
- 意味や目的を重視する姿勢
- 持続性と創造性を自然に発揮
例えば、語学学習を考えてみてください。「上司に言われたから」「昇進に必要だから」という理由で英語を学ぶ人と、「海外のお客様と直接やり取りしたい」「異文化を理解したい」という想いで学ぶ人では、どちらが継続し、どちらが応用力を身につけるでしょうか?

自律型人材と内発的動機づけ
前回お伝えした「自律型人材(SLT:Self Leadership Talent)」は、まさに内発的動機づけによって動く人材のことです。VUCA時代に求められる「自分で考え、判断し、行動できる人材」の根底にあるのが、この内発的動機づけなのです。
しかし、現実の多くの職場では、依然として外発的動機づけが中心となっています。売上目標、KPI、評価制度など、外部からの刺激で人を動かそうとするアプローチが主流です。
なぜ内発的動機づけのアプローチを採用しないのでしょうか?
それは、内発的動機づけという概念そのものを知らないか、知っていても「どう実践すればいいか分からない」からです。多くの管理職が「やる気を出せ」「主体的に動け」と言いますが、具体的にどうすれば内発的動機が生まれるのかが見えていません。
つまり、自律型人材を育成するということは、内発的動機づけを引き出す関わり方を実践するということなのです。では、この内発的動機づけを引き出すために、どのような関わり方や環境づくりが必要なのでしょうか?
実は、その答えのカギを握っているのが、管理職自身の動機の質なのです。部下を育成する立場にある人が、外発的動機で動いているか内発的動機で動いているかによって、部下育成の結果は劇的に変わります。
理論だけでは実感しにくいかもしれません。実際の管理職の事例で、動機の質が部下育成にどう影響し、自律型人材の育成にどうつながるかを見てみましょう。
動機の違いが生み出す決定的な差:2人の管理職の対比
外発的動機づけ中心の管理職Cさん
役割:営業部課長、部下8名のマネジメント
動機:「部署の数字を上げて評価されたい」「昇進につなげたい」(外発的)
部下育成のアプローチ
- 月次の数値目標を厳格に管理
- 未達者への個別指導で叱責中心
- 成果を出した部下のみを評価・優遇
- 「結果がすべて」という姿勢を徹底
6か月後の結果
- 短期的には数字が向上したものの、部下の離職率が上昇
- チーム内の協力関係が悪化し、情報共有が停滞
- 新しい提案やアイデアが出なくなった
→ 自律型人材は育たず、指示待ち人材が増加
内発的動機づけ中心の管理職Dさん
役割:営業部課長、部下8名のマネジメント
動機:「部下の成長を支援したい」「お客様により良い価値を提供したい」(内発的)
部下育成のアプローチ
- 個人の価値観と仕事の意味を一緒に見つける
- 失敗を学習機会として捉え、改善を支援
- プロセスでの努力や工夫を積極的に承認
- 「顧客価値の創造」を共通目標として設定
6か月後の結果
- 数字も向上し、かつ部下のエンゲージメントが大幅に改善
- チーム内の相互支援が活発化し、集合知を発揮
- 部下からの自発的な改善提案が増加
→ 部下が自律型人材として成長し、チーム全体の自律性が向上
同じ条件でも結果が変わる理由:自律型人材育成の分岐点
管理職自身の「動機の質」が、すべての始まり
CさんとDさんの事例から見えてくるのは、部下育成の結果を決定づけるのは、管理職自身の動機の質だということです。
同じ営業部課長、同じ部下8名という条件でも、2つの全く異なる循環が生まれました:
外発的動機づけの循環:従来型人材の再生産
管理職の外発的動機 → 統制・競争重視の育成 → 部下も外発的動機に → 指示待ち人材の増加 → さらなる管理強化の必要性
Cさんのケース:「評価されたい」という外発的動機 → 数値管理・叱責中心 → 短期的な数字向上も離職率上昇 → 自律型人材は育たず
内発的動機づけの循環:自律型人材の自然発生
管理職の内発的動機 → 支援・協働重視の育成 → 部下も内発的動機に → 自律型人材の成長 → 自律的な改善の継続
Dさんのケース:「部下の成長支援」という内発的動機 → 価値観の共有・プロセス承認 → 数字も向上しエンゲージメント改善 → 自律型人材が育つ
興味深いことに、Dさんも最初はCさんと同じような管理職でした。数字を追い、部下を厳しく管理していたDさんが、ある出来事をきっかけに自分の内発的動機に気づき、アプローチを180度転換したのです。
同じ人でも、動機の質を転換することで、異なる結果を生み出せる──これが、自律型人材(SLT)育成のカギです。
では、Dさんはどのように外発的動機から内発的動機に転換していったのでしょうか?その具体的なプロセスは、第8章「管理職:統制から支援への転換」で詳しくご紹介します。Dさんに起きた内面の変化から実践的な行動変容まで、時系列でお伝えします。
動機の質が組織に与える長期的影響:自律型組織への変化
動機の質の違いは、個人レベルだけでなく、組織全体に長期的な影響を与え、最終的に「自律型人材」の育成によって、「従来型組織」が「自律型組織」へと変化を遂げていきます。
外発的動機づけ中心の従来型組織
- 短期的な成果は出やすいが、持続性に課題
- 環境変化への適応力が低い
- 指示待ち人材が多く、管理コストが増大
- イノベーション創出が困難
内発的動機づけ中心の自律型組織
- 持続的な成長と改善を実現
- 変化への適応力が高い
- 自律型人材が多く、管理コストを削減
- 自然とイノベーションが生まれる土壌
組織の変化については、第10章で詳しくご紹介します。
心理学の科学的基盤
ここまで見てきた内発的動機づけの力には、実は確かな科学的根拠があります。心理学の「自己決定理論」が、その秘密を解き明かしてくれるのです。
この理論によると、人が内発的にやる気を持ち続けるには、3つの心理的欲求が満たされる必要があるとされています:
- 自律性:「自分で選んでいる」という感覚
- 有能感:「自分はできる」という実感
- 関係性:「人とのつながりや信頼」を感じられること
つまり、この3つの欲求を満たす関わり方や環境を整えることで、人は自然と自律的に行動するようになるのです。
次章では
なぜ人は「やりたい」と感じるのか、その科学的メカニズムを自己決定理論に基づいて解説します。人が変わるのは、外からの力ではなく、内からの力によってです。より確実で持続可能な人材育成を実現するための具体的な方法論を、一緒に学んでいきましょう。