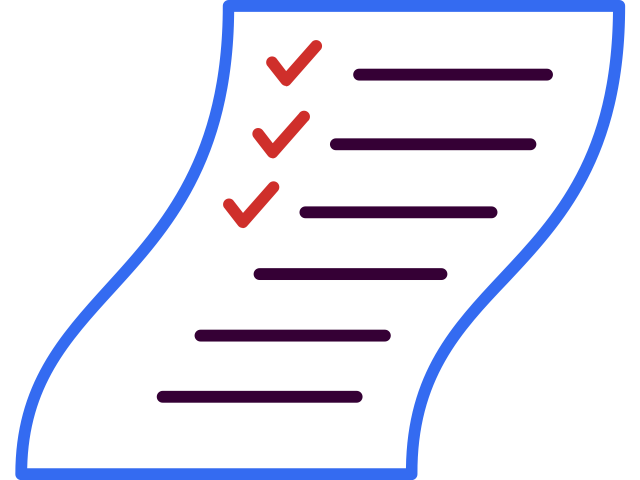マインドフルネスに関わる研究事例
マインドフルネスに関わる研究事例をご紹介します。海馬、扁桃体、前帯状皮質、デフォルト・モード・ネットワークなどの部位別に、様々な研究が行われています。未経験者でも8週間のマインドフルネスの実践で神経可塑性が発揮され、海馬や扁桃体に変化が起こることが示されたり、実践者では注意の処理に関わる前帯状皮質に変化が見られたり、デフォルト・モード・ネットワークが鎮まることが確認されています。メタ分析(科学的に最も信頼できる調査手法)では、実践者の脳の8つの領域で構造変化が見られたと報告されています。
海馬
海馬は、記憶や空間認識に関わる領域で、30秒くらい継続する短期記憶を担っています。短期記憶は、何かの作業をするために短い時間だけ覚えておく必要のある記憶で、その作業が終わってしまえば忘れてしまうもので、ワーキングメモリ(作業記憶)とも呼ばれます。実は、海馬は記憶以外にも知覚プロセスにおける重要な役割を果たしており、学習や感情制御の調節に関与しています。また、ストレス等で委縮すると、うつ病の原因になると指摘されている部位です。
マインドフルネスを実践することで、海馬の灰白質の体積が増大することが確認されています。記憶力や学習プロセスを向上させ、仕事の作業効率を高めたり、迅速で正確な意思決定をする上で必要となる判断力を向上させたりすることが見込まれます。本研究によれば、8週間のマインドフルネスの実践により海馬の灰白質が増加し、萎縮していた海馬が回復したことが明らかになりました。
| 研究タイトル |
「マインドフルネスの実践は脳の灰白質を増加させる」 |
| 時期 |
2010年 |
| 実施者 |
マサチューセッツ総合病院、ハーバード・メディカルスクール、ユストゥス・リービッヒ大学ギーセン(独)他 |
| 被験者 |
MBSR(※)参加者16人と非参加者17人、平均年齢38歳 |
| 内容 |
MBSR8週間プログラム(平均27分/日)実践前後のMRIデータを解剖学的に分析 |
| 結果 |
左海馬、後帯状皮質、側頭頂接合部、および小脳の灰白質の体積増加を確認した。 |
| 考察 |
MBSRへの参加が、学習および記憶プロセス、感情調節参照処理に関わる脳領域を増加させると考えられる。 |
(※) MBSRは、Mindfulness Based Stress Reductionの略で、マインドフルネスのストレスマネジメントのプログラム名称
この事例は、2010年にマサチューセッツ総合病院、ハーバード・メディカルスクール等が実施した研究結果です。健康な未経験者16人が8週間のマインドフルネスプログラム(MBSR)を実践し、その前後にfMRIで画像解析を行い17人の非実践者と比較するという研究内容です。結果は、マインドフルネスの実践前後で、左海馬内の灰白質体積が5%増加したことが確認されました(※1)。下図は、海馬の画像解析結果と灰白質の変化を比較したグラフです。海馬の構造が変化しているという結果は、学習および記憶プロセス、感情調節、自己参照処理を改善することを示唆していると考えられています。また、同研究で、実践者たちの後帯状皮質、側頭頂接合部、および小脳の灰白質濃度の増加が明らかになりました。

扁桃体
扁桃体は、情動の中枢としての役割を担い、さまざまな種類の情動に関わりますが、特に恐怖や不安に深く関与することが知られています。過度な不安や恐怖が症状であるうつ病、不安障害やPTSDといった精神疾患においては、扁桃体の活動が過剰であること知られています。たとえば出来事においてネガティブな側面ばかりに注目してしまったり、それを必要以上に覚えてしまったりするという情報処理上の偏り(バイアス)が生じる可能性が指摘されています。反対に統合失調症や自閉症に認められる感情や対人コミュニケーションの障害が扁桃体の活動の低下と関連していることも知られています。
マインドフルネスを実践することで、扁桃体の灰白質が減少することが確認されています。偏桃体が小さくなると、ストレスに過剰反応しにくくなります。本研究によると、8週間のマインドフルネスの実践で扁桃体の灰白質の体積が5%減少し(※2)ストレスレベルが低下したことが明らかになりました。
| 研究タイトル |
「ストレス低減が扁桃体の構造変化に関わる」 |
| 時期 |
2010年 |
| 実施者 |
マサチューセッツ総合病院、ハーバード・メディカルスクール、ユストゥス・リービッヒ大学ギーセン(独)他 |
| 被験者 |
調査前月に高いストレス状態であった26人(8週間で平均20時間の実践) |
| 内容 |
- MBSR8週間プログラム実践前後のMRIデータを解剖学的に分析
- 主観的評価によるストレステスト(PSS)
|
| 結果 |
- 右扁桃体の灰白質の体積減少を確認した。左扁桃体には変化がなかった。
- 実践時間が長い人ほど主観的評価によるストレスレベルは減少した。
- ストレスレベルが減少した人ほど右扁桃体の体積の減少度合いが大きかった。
|
| 考察 |
右扁桃体に変化があり、左扁桃体に変化がなかったのは、「右扁桃体が即座に刺激知覚をするのに対し、左扁桃体は刺激を知覚した後に評価や識別をする機能を果たしている」という説を支持していると考えられる。 |
この事例は、2010年にマサチューセッツ総合病院、ハーバード・メディカルスクール等が実施した研究結果です。高いストレス状態にある未経験者26人が8週間のマインドフルネスプログラム(MBSR)を実践し、主観的なストレスレベルの評価とその前後にfMRIで画像解析を行った研究内容です。結果は、マインドフルネスの実践前後で、主観的なストレスレベルは低下し、右扁桃体の灰白質体積が減少したことが確認されました。また、ストレスレベルが低下した人ほど、右扁桃体の灰白質体積の減少度合いが大きいことが分かりました。
下図は、扁桃体の画像解析結果と右扁桃体の減少度合いとストレスレベルの変化の関係性を表したグラフです。マインドフルネス瞑想でストレスが軽減された感覚になるのは、単なる気の持ち用ではなく生物学的に変化をしたことを示唆していると考えられています。

(※1)(※2)NHKスペシャル「キラーストレス」(2016年6月19日放送)サラ・ラザー教授インタビュー
前帯状皮質
前帯状皮質は、大脳半球内側面の前方部に存在し、その領域に応じて、行動調節、社会的認知、情動に関わります。以下の2つは、行動調節とマインドフルネスに関わる研究です。行動調節とは、意図的に注意を向けたり行動を導いたり、不適切な無条件反射的な反応を抑えたり、戦略を柔軟に切り替えることを意味しています。前帯状皮質に損傷がある人は、衝動性や抑えきれない攻撃性を示します。そして、前帯状皮質と他の領域のつながりに損傷があると、心理的柔軟性のテストの点数が低くなり、行動を調節するよりも効果的でない問題解決方法にしがみつきます。
一方で、マインドフルネス実践者は非実践者に比べて、行動調節のテストでより優れた能力を発揮し、注意を逸らすものに耐え、正しい答えを選ぶことができます。実践者は、非実践者よりも前帯状皮質がより活性化していることが確認されています。行動調節に加えて、前帯状皮質は、適切な意思決定をするための過去の経験からの学習に関わっています。科学者たちは、前帯状皮質の働きが、不確実で変化が激しい状態においては、とりわけ重要であると指摘しています。
| 研究タイトル |
「より高い注意の処理能力とマインドフルネス瞑想の関連」 |
| 時期 |
2010年 |
| 実施者 |
ナイメーヘン・ラドバウド大学 |
| 被験者 |
マインドフルネス実践者20名と非実践者20名 |
| 内容 |
- 注意の処理に関わるテスト
- 反応時間と正確さの相関性
|
| 結果 |
- 実践者の方が、より順応性と注意の実行が高いことが観察された。
- さらに経験豊富な実践者は、同じ反応時間での誤回答率が減少した。
|
| 考察 |
- マインドフルネスの実践に応じて注意の処理に違いが生まれる。
- 心のトレーニングによって注意の処理能力が高まる可能性を示している。
|