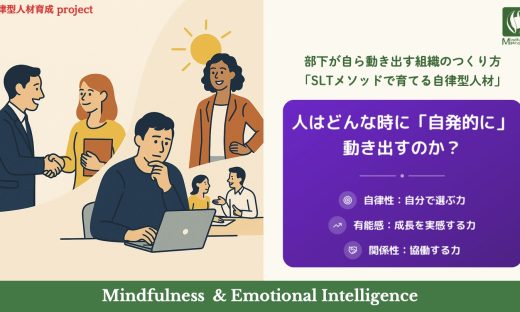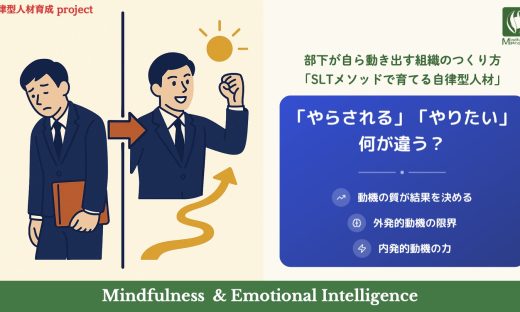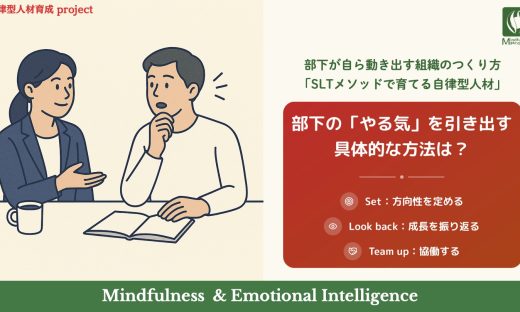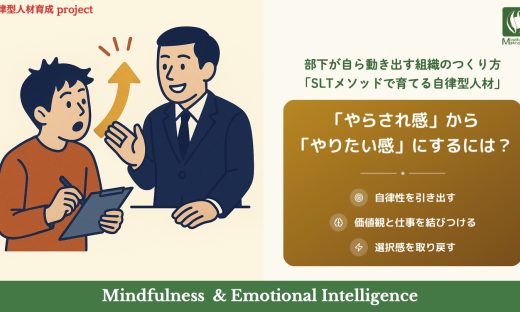第1章:なぜ今、指示待ち人材では通用しないのか? | 部下が動かない本当の理由|「自律型人材」という選択
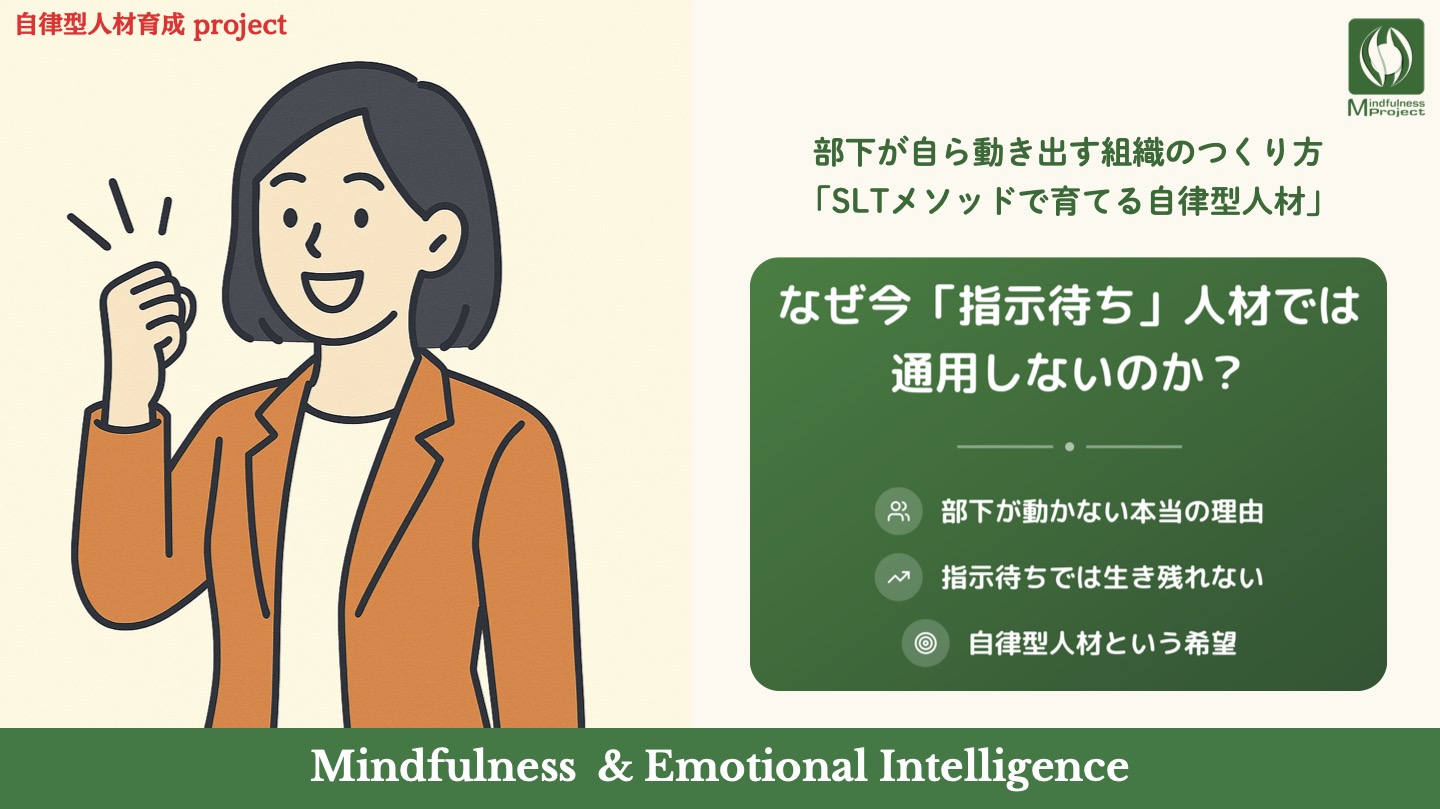
月曜日の朝、こんな光景を目にしたことはありませんか?
朝礼で新しいプロジェクトを発表したとき、部下の反応を見回すと…
「また面倒なことが降ってきた」という表情で下を向く人。
「誰がやるんだろう?」と周りを見回している人。
一方で、積極的に「どのように進めましょうか?」と前のめりに質問してくる人は、10人中1人いるかどうか。
「なぜ同じ部下なのに、こんなに反応が違うのだろう?」
管理職の方からこんな声をよく聞きます:
「朝礼で目標を発表しても、部下の反応が薄い。以前なら積極的な質問が出たのに、最近は静かに聞いているだけ。会議でも『どう思う?』と聞いても沈黙が続く。指示待ちの部下が増えている気がするのですが、何が原因なのでしょうか?」
もしかすると、あなたも似たような経験をお持ちではありませんか?
指示待ち人材は、昔から存在していた
実は、こうした「指示待ち」の部下は、今に始まったことではありません。10年前も、20年前も、言われたことだけをやる人は一定数いました。
しかし、以前はそれでも組織は回っていました。
なぜなら、ビジネス環境が比較的安定していたからです。上司が正解を知っていて、決められた手順を忠実に実行すれば成果が出る。そんな時代だったのです。
指示待ちの部下が多少いても、上司が的確に指示を出せば、組織全体として機能していました。ところが今、同じやり方では組織が機能しなくなってきています。
なぜでしょうか?
VUCAの時代──指示待ちでは生き残れない
なぜなら、私たちが働く環境そのものが大きく変化したからです。
この変化を、ビジネスの世界ではVUCAと呼んでいます。コロナ禍で一夜にしてリモートワークが必須になり、AI技術の進歩で「5年後の仕事」が予測不可能になり、「正解」が複数存在する複雑な時代です。
VUCA時代の今、何が変わったのか?
- 上司も正解が分からない(前例がない状況が日常化)
- 決められた手順では対応できない(想定外が当たり前)
- 指示を待っている間に状況が変わる(スピードが致命的)
つまり、「上司が決めた正解を、部下が忠実に実行する」という従来の働き方では、もはや対応できないのです。
指示待ち人材が多い組織は、今、急速に競争力を失っています。
2020年3月の緊急事態宣言を思い出してください。
- すぐに動き出したメンバーは、「お客様への連絡方法を変更しなければ」と自ら準備を始めました。
- 指示を待っていたメンバーは、「会社から連絡があるまで待とう」と受け身の姿勢を続けました。
この違いを生んだのは、「自分で考え、判断し、行動できる人材」──自律型人材がいたかどうかだったのです。
昔なら許容できた「指示待ち」が、今は組織の生き残りを左右する決定的な弱点になっているのです。
自律型人材という希望
このような時代の変化の中で、どんな人材が求められているのでしょうか?
それは自律型人材です。
自律型人材とはどんな人材か?
自律型人材とは、以下のような特徴を持つ人材です:
- 自分で考え、判断し、行動できる人
- 自分で課題を見つけ、解決策を創造できる人
- 周囲と協力しながら前進できる人

- 「前例がない」状況でも、お客様視点で何ができるかを積極的に模索する
- 失敗しても学習機会として捉え、次の改善につなげていく
- 同僚が困っていると気づいたら、自然と声をかけて協力を申し出る
自律型人材は、ただ「自分勝手に行動する人」とは全く異なります。組織の目的や価値を理解した上で、自分なりの判断と責任を持って行動する人材なのです。
自律型人材が組織にもたらす3つの価値
では、自律型人材は組織にどんな価値をもたらすのでしょうか?あなたの職場で起こりうる具体的な場面で見てみましょう。
① スピード:現場での即断即決力
お客様から突然「来週までに提案書がほしい」という急な依頼が入った時:
従来型メンバーは、「上司に相談してから」と一旦持ち帰り、結果的に「間に合いませんでした」と報告。
自律型メンバーは、その場で要件をヒアリングし、翌日には骨子を作成。早めに中間確認も実施。
② 創造性:新たな価値創出力
毎月3日かかっていた報告書作成業務で:
従来型メンバーは、「決められた通りにやらなければ」と手作業でデータを転記し、効率化を考えない。
自律型メンバーは、「このデータ転記、自動化できないかな?」とExcelの関数を調べ、「お客様が本当に知りたいのは何だろう?」と構成を見直し。結果、3日の作業が半日に短縮。
③ 継続力:持続的なモチベーション
新システム研修で:
従来型メンバーは、「上司に言われたから」参加し、基本操作だけ覚えて終了。
自律型メンバーは、「お客様により良いサービスを」と考え、研修後も自分で調べて効率的な使い方を発見し、半年後には「お客様から感謝される機会が増えました」と報告。
あなたのチームでも、人によって反応が全く違いませんか?
ある案件では積極的に取り組む人がいる一方で、別の人は消極的になる。同じ研修を受けても、活用する人と忘れてしまう人がいる。
こうした反応の違いは、能力や性格の問題ではありません。実は、人間の心理に関する明確な法則があるのです。
なぜ「やらされる人」と「やりたい人」に分かれるのか?
この違いを生み出しているのは、「動機の質」という心理学的な法則です。この法則を理解し、いくつかの条件を整えるだけで、多くの人が自然と「やりたい」気持ちになることが、30年以上の心理学研究で明らかになっています。
この方法を知った管理職の方からは、
- 「指示を出さなくても、部下が自分から動くようになった」
- 「会議での発言が激増した」
- 「離職率が大幅に改善した」
という報告が続々と寄せられています。
次章では
「動機の質」に焦点を絞ります。「なぜ『やらされる人』と『やりたい人』に分かれるのか」。その根本的な違いを、あなたの職場での具体例とともに詳しく解説します。きっと「だから、あの人はいつもやる気があるのか!」という発見があるはずです。
変革への第一歩
このコラムシリーズでは、自律型人材育成の具体的な方法論を、理論と実践の両面からお伝えしていきます。明日からあなたのチームで活用できる実践的なアプローチを中心に、全10回にわたって詳しく解説します。
特に、このシリーズの核となるのがSLTメソッドです。SLTとはSelf-Leadership Talent(自律型人材)の略で、3つのステップから成る実践的なフレームワークです:
- S – Set your direction(自分の方向性を定める)
- L – Look back at your growth(成長を振り返る)
- T – Team up with respect(尊重を持って協働する)
第1-3章で理論の基盤を理解し、第4章でSLTメソッドの全体像を把握し、第5-7章で各要素の実践方法を学びます。そして第8-10章で、現場での応用事例や組織での活用方法を具体的にお伝えします。